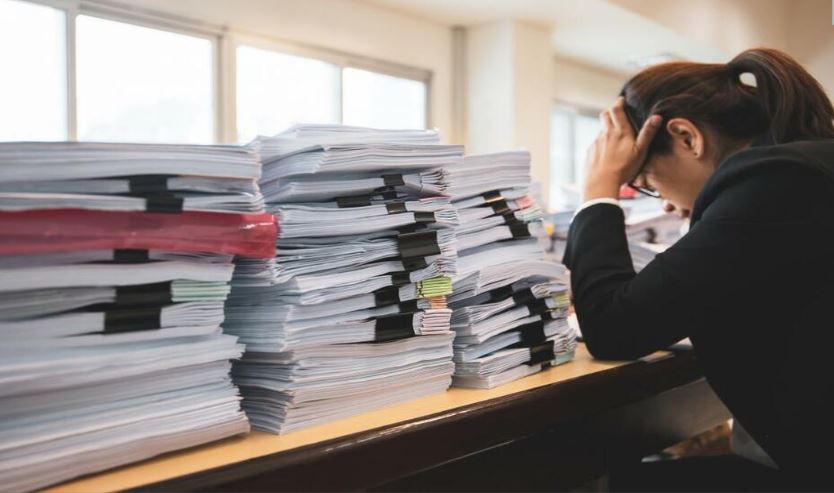なぜこうも疲弊する教育現場が増えているのか。
教員にのしかかる負担は計り知れない。
教育改革実践家の藤原和博氏は、新著『学校がウソくさい 新時代の教育改造ルール』で、
悲鳴が上がる現場を改革するために必要なことを述べている。
同書から一部を抜粋、再編集し、紹介する。
学校現場が書類仕事にまみれ、教員たちが事務処理に喘いでいることはもはや常識だ。
それゆえ、熱心な先生ほど、児童生徒の学習や生活に寄り添えないことを苦にして行き詰まってしまう。
精神的なバランスを崩したり、先生なのに不登校になってしまったり。
おまけに保護者からの無体なクレームも増えるばかりだ。
2022年度に実施した公立校教員の勤務実態調査の速報値が4月に公表されたが、
1カ月あたりの残業時間は、中学校で8割弱、小学校で6割強の教員が文科省の定める上限基準に達していた。
長時間労働が常態化しているのだ。
この状況を根本的に変えることなしに、どんな前向きな教育改革も意味をなさない。
教員志望の大学生が減っている現状は、この問題の解決が急務であることを教えてくれている。
では、どこから変えるべきだろうか?
まず、教育委員会がリスクを取って、「書類仕事ゼロ」を目指すことから始めるしかない。
もちろん、ゼロを目指して半減すれば上出来だ。
私が、民間校長になってまず驚いたのは、教育委員会から届く書類の膨大さだった。
2003年当時で、週に100枚近くはあったと思う。
この話を最近ある現役校長にしたら、
「それ、1日に届く数の間違いじゃあないですか?」と返され、絶句した。
しかも、学校現場のマネジメント側のICT化が遅れたせいで、現在はその移行期であるためか、紙の書類とネットでのデジタルファイルが二重に届く自治体もあるらしい。
それが実態だ。
こんなものをまともに読んでいたら、それ自体が仕事になってしまう。
実際、教頭はそうした文書業務で忙殺される。
しかも、その文書のほとんどを作っているのは「指導主事」という名の教員だ。
教育委員会側の教員なのだ。
実にもったいないと思う。
この膨大な書類仕事をゼロにできれば、書類を作って出す方の指導主事と、学校現場で受ける方の教頭を合わせて、全国で約10万人が教員本来の仕事に戻れるのだから。
はっきり言おう。
教員が足りないというより、文書仕事が多過ぎて、指導主事と教頭が死んでるから
本来の仕事に手が回らなくなってしまっているということだ。
まず、要らない書類は何か。
何よりも筆頭に挙げたいのは、「アンケート」だ。
例えば、いじめ自殺問題がマスコミで大きく報道されると、
国会議員が国会で文科省に「どうなってるんだ!」と質問する。
文科省はデータを持っていないから、アンケートを作って都道府県の教育委員会に降ろす。
「学校では、日常的にいじめに目を光らせていますか?」
「いじめの発見のためのアンケートを毎学期とっていますか?」
「発見した場合、どのように対処していますか?」と多数の項目が並ぶ。
都道府県でも都道府県議会議員が同じような質問をするから、都道府県教委も独自にアンケートを作って降ろしてくる。
さらに、小中学校の場合は市区町村が設置者だから、市区町村議会議員が議会で質問すると、ここでも、もっと詳細なアンケートが作られる。
つまり、一つ課題が生じると、国と都道府県と市区町村が三重にアンケートを作って学校に降ろしてくるというわけだ。
もちろん、いじめや自殺は大事件だから大騒ぎも当然だし、対処しないのは言語道断だ。
しかし、食育についてとか、尖閣諸島や北方領土の地理での扱いについてとか、「こころの教育」についてとか、リモート教育についてとか、マスクについてとか・・・
アンケートが多岐にわたって際限がない場合は何とかするべきだろう。
究極的な結論から言えば、データがあれば、アンケートは要らない。
であれば、データを持てばいい。
学校現場のDX化を進めて日々のデータが常にアップデートされるようにしておけば、
究極は、学校現場のすべてが上位者である教育委員会や文科省にも共有され、いちいちアンケートなどをその都度とる必要はなくなるはずだ。
個人情報保護条例から懸念があるかもしれないが、
そもそもこれは児童生徒の利益に関わることなのだ。
本来ならば、児童生徒を守り育てるのが教員の仕事である。
その教員の時間がデータ収集作業に邪魔されているのだから、アンケート業務は当然見直されるべきだと思う。
どうしても必要な「学校基本調査」を含めて、アンケートは1学期に1本くらいに絞ればいい。
もう一つ、保護者は気づかないだろうが、
現場を不必要に忙しくさせている「学校を通じた作品や児童生徒の募集」という悪弊がある。
例えば、国税庁からの依頼だと思うが、
小中学生に「税金の作文」を書かせ、それなりの審査員を立てて、受賞者を表彰することが行なわれている。
省庁からすれば一種のPR活動であり、国民に関心を持たせる広報行為だ。
しかし、小中学生は本当に「税金の作文」を書きたいだろうか?
私は疑問だ。
税金を納めることは国民の義務だし、その教育を行なうことは否定はしない。
しかしもっと知恵を絞れば、ゲームを使って広報するようなやり方もあるのに、とつくづく思う。
ことほど左様に、児童生徒の募集や作品の募集が無数に学校を通じて行なわれるのだ。
ポスターや募集要項が送られてくると、その都度、教頭が下駄箱の横の掲示板にポスターを画びょうでとめ、案内を各クラスの担任に配布する。
恐縮だが、私は校長として、学校を流通網として使う行為はほどほどにすべきと感じたので、
ほとんどのポスターは貼らないで良いと教頭に命じた。
もちろん、拉致問題のキャンペーンポスターなどは例外だ。
藤原和博(教育改革実践家)
1978年、東京大学経済学部卒業後、現在の株式会社リクルート入社。
東京営業統括部長、新規事業担当部長などを歴任し、93年よりヨーロッパ駐在、96年、同社の初代フェローとなる。
2003年から、都内では義務教育初の民間校長として杉並区立和田中学校の校長を務める。
2016年から、奈良市立一条高等学校校長。
2021年、オンライン寺子屋「朝礼だけの学校」を開校する。
著書多数